自動車解体業、自動車破砕業のご相談、ご依頼は大阪府八尾市の石井行政書士事務所072-949-5214
豊富な経験と蓄積された知識から知恵を創出し、依頼案件の可能性に挑戦します
現在位置 : 石井行政書士事務所TOP >>自動車解体業・破砕業
自動車解体業、破砕業の許可や更新、変更申請に関することは石井行政書士事務所にお任せください
中古自動車や鉄くず業に関わる業者さんへ!
許可が必要な業者さん
自動車の解体業・破砕業
使用済車の部品やパーツを取るすべての業者
登録が必要な業者さん
自動車引取業
新車・中古車・整備業者・直取りの解体業者
フロン回収業
無許可での操業には下記の二法による取り締まりと厳罰
ところで現在も無許可で操業されている自動車業者さん!解体業の許可を取得しないと大変なことになりますよ!
無許可で使用済車の部品取りを行った場合は厳罰処置!
自動車リサイクル法違反
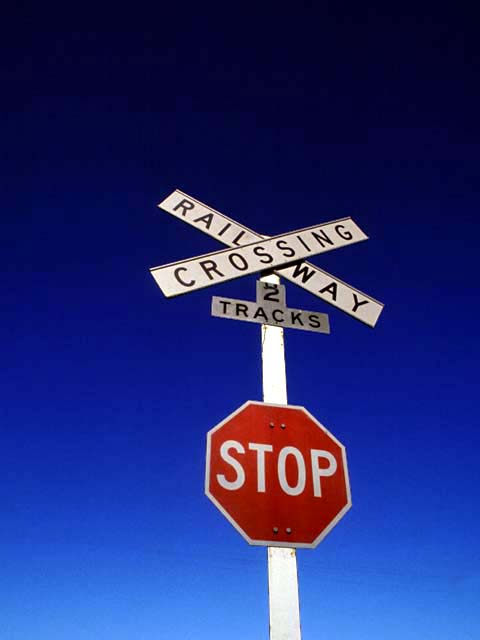
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
廃棄物処理法違反
5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
日ごろ慣例的に行っているパーツ取りなどは立派な法律違反。自動車整備業を営んでおられる事業者の方で解体業・処分業に該当すると思われる方は特にご留意ください。内部告発や摘発もありますよ!
もし摘発されでもしたら新聞沙汰になって大変です。まずは無料相談メールを
自動車解体業・破砕業の許可を得るために何が必要か?
自動車リサイクル法(以下自リ法という)では電子マニフェストを採用するため、原則としてはインターネットの環境下にあるパソコンを操作できないことには業務を遂行することができません。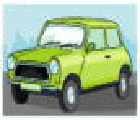
特例としてFAXによる送信も認められていますが、データを打ち込んでもらう手数料を支払わないといけません。
-
あなたの事業所ではインターネットができる環境が整っていますか?
-
インターネットを容易に扱えますか?
パソコンもないし、あっても扱えない。でもご心配無用!
当事務所では専属の講師を派遣してあなたをサポートいたします。
自動車リサイクル法とは? その全体像
1.使用済み自動車の流れ(一体どんな法律なの?)
自動車製造業者等(輸入業者を含む)は自ら製造・輸入した自動車が使用済み(つまりは廃車ということ)になった場合、シュレッダーダスト、エアバック類、フロン類(フロン類については破壊)を引き取ってリサイクルを行う義務を負うべきだという考え方(これを拡大生産者責任といいます)が根底にあります。
つまり、自動車を販売した者は廃車後も責任を持ってリサイクル(再資源化)、破壊を行いなさいよ、というのが自動車リサイクル法の趣旨なのであります。
したがってこの法を確実なものとするためには、自動車の流通に関わるすべての業者が、例外なく道府県知事等の登録・許可を受けることによって、それぞれの立場、役割の中で、一定の義務を負うこととなります。
2.リサイクル料金等の流れ(料金は誰が払うのか)
では料金は誰が払うのか? と申しますと、これは自動車の所有者が支払うことになっています。ただしその後の業者間の料金については当事者間の協議で決定されることになっています。
リサイクル料金はあらかじめ自動車製造業者(輸入業者を含む)が定め、公表することになっています。これは自由競争を促すことによって不適切な料金を排除しようとする考え方です。
リサイクル料金は原則として新車販売時に購入者が負担、負担金は資金管理法人(財団法人自動車リサイクル促進センター)に預託金という形で保管されます。こうすることでリサイクル料金は安全確実に保管利用されることになります。
3.実際の流れ(使用済みの車がリサイクルされるまでの業者間での流れ)
電子マニフェスト(移動報告)制度を導入することで、各工程での適切な引き取り・引き渡しがなされていることを確認できるようになります。監督する側としては抜き打ち検査が可能だということです。
実務上はパソコンから情報管理センターに報告することになっています。ですから事業所にパソコンを装備されていないと、業務そのものが遂行できない、つまりは業務ができないということになります。許可業者さんにとってはネット環境下にあるパソコンは必携品です。
4.対象とならない自動車
-
被牽引車
-
二輪車(原動機付き自転車、側車付のものをふくむ)
-
大型特殊自動車、小型特殊自動車
-
その他政省令で定めるもの
農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車製造業者等の試験・研究用途車、ホイール式高所作業者、無人搬送車 -
そのほか、架装物部分については再利用されることが多いことから原則として対象外となっていますが、今後実情を鑑みたうえで線引きがなされるようです。
自動車リサイクル法と産業破棄物処理法との関係
自動車リサイクル法の登録・許可を受けた業者については、使用済み自動車を運搬・処理をするにあたっては破棄物処理法の許可は不要となります。
事業所所在地の都道府県知事等の登録・許可を受けていれば他都道府県でも収集運搬が可能です。ただし運搬・処理をするにあたっては破棄物処理法に基づいて行わなければならいことは当然のことです。
自動車リサイクル法の登録・許可業者は、次の行程となる登録・許可業者に引き渡す義務がありますが、電子マニフェストが適用されるため、従来の紙面等のマニフェストは不要となります。
フロン回収破壊法との関係については原則としてその枠組みは自動車リサイクル法に引き継がれています。
つまりフロン回収破壊法の登録第二種特定製品取引業者、第二種フロン類回収業者は、自動車リサイクル法の引取業者、フロン類回収業者の地位(標識を掲示する必要あり)に自動的に移行することになります。
なお登録業者のフロン券による費用徴収方法は自動車リサイクル法の費用徴収方法に一本化され、つまりは電子マニフェスト制度となります。
作業場改築のために必要な資金融資申請をサポート
許可を取得するには設備的な改築改造を必要とします。ついては資金融資を必要とされるお客様のために、融資の申請に必要な事業計画書等の作成サポートも行っております。そうしたことも含め、まずはご相談下さい → 無料相談メール
フロン引取・回収業者申請無料代行をサポート
また当事務所は電子申請をにらんだパソコン導入のご相談や設定指導等、さらに事業拡張に向けた自社HP作成のお手伝いなどもサポートしております。どうかお気軽にご相談下さい → 無料相談メール
許可申請に最低限必要な書類
自動車リサイクル法に基づく許可を申請するには、下記のような書面を取りそろえ、それぞれ記載する必要があります。
| No | 取り揃える書類や書面 |
| 1 | 申請者の住民票(外国人登録証明書) |
| 2 | 申請者の登記事項証明書 |
| 3 | 誓約書 |
| 4 | 施設の構造を明らかにする図面 |
| 5 | 設計計算書 建物平面図立面図・設計図等 床の状態=鉄筋入りコンクリート |
| 6 | 付近の見取り図 (内容によっては付近住民の承諾が要る場合もあります) |
| 7 | 施設の所有、使用権原を証明する書面 ・賃貸借契約書原本提示(申請はコピー) ・登記簿謄本(原本) ・地積公図(原本) |
| 8 | 解体業による収益・支出(財務諸表より拾い出す) 年間解体実績 台? 今後の見込み 台? |
| 9 | 事業計画書及び収支見積書(財務諸表や決算資料等より書き移すこと。 いい加減な数字では認められない。 |
| 10 | ・標準作業書 (自社車両・写真ナンバー) ・産廃委託処理業者(廃油の収集運搬業・中間処理業者) ・委託処理業者(収集運搬業・中間処理業者) |
| 11 | 危険物保安監督者の選任 消防法や市条例等により異なる場合があります。 |
| 12 | 高圧ガスを使用するか否か? 保安法に拠る |
| 13 | アセチレン溶接装置等使用するか否か? 労働安全衛生法に拠る |
| 14 | 緊急通報体制 第一発見者 作業責任者 事業所責任者 |
| 15 | 解体済車の引渡破砕業者名 |
| 16 | 消防法・市町村条例を遵守した危険物保管体制の確保 |
| 17 | 事業所所在地の公害防止条例等の調査確認 |
| 18 | 事業所所在地の用途地域の確認 (原則として住居地域では許可が下りません) |
| フロン関係申請手続 | |
| 19 | フロン回収機器のカタログ・仕様説明書(コピー) |
| 20 | 回収装置の種別 CFC・HFC・兼用型 |
解体業・破砕業の許可要件
許可を申請するには以下の三つの基準に適合する必要があります。
①施設にかかる基準
| 解体業者施設 | 許可の要件 | |
| 引き取った使用済自動車を解体するまでの間保管するための施設 | 特に施設が解体作業場以外の場所にあるような場合 | ①みだりに人が出入りできないような囲いがあり、かつ、当該場所の範囲が明確であること(規則57条) ②廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合、その防止をするために必要な措置が標準作業書等から確認、明らかであること(規則57条) ・廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 ・廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。 |
| 解体作業場 | 右の要件を満たす解体作業場を有すること | ①使用済自動車から廃油(燃料を除く)及び廃液を回収するための装置を有すること。 ただし、手作業で行う場合、適切かつ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らかな場合はこの限りでない。 ②廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 ③廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。 ただし、解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少なく、かつ、廃油の事業所からの流出をぼうしするために必要な措置が講じられていることが標準作業書の記載から明らかな場合はこの限りではない。 ④雨水等により廃油及び廃液が事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための施設を有すること。 ただし、当該設備の設置が著しく困難な場合であり、かつ、雨水等による流出を防止するために十分な処理能力を有する雨水分離装置を設けることなどの措置が講じられている場合はこの限りではない。 |
| 燃料搾取場所 | 解体作業場以外の場所で燃料抜き取りを行う場合 | ①廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 ②廃油の事業所からの流出を防止するため、「溜めます」その他これと同等以上の効果を有する装置及びこれと接続している排水溝を設けられていること。 |
| 取り外した商品の保管場所 | 解体作業場以外の場所で取り外した部品のうち廃油及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合 | 標準作業書において防止の措置が記載されてあればOK! ①廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 ②廃油の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該商品に雨水等がかからないようにするための施設を有すること。 |
| 解体自動車の保管 | 解体した後に残る廃車ガラを保管するための施設 | 上記、使用済自動車を保管するための施設と同様 |
| 破砕業者施設 | 許可の要件 | |
| 解体自動車を破砕前処理又は破砕するまでの間保管するための施設 | 上記、解体業の使用済自動車を保管するための施設と同様 | |
| 破砕前処理施設 | プレス又はせん断のための施設 | 三方締めプレス・一方締めプレス プレスを行う場合にあたっては、産廃物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動に拠って生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設を有すること。(規則62条) |
| 破砕施設 | シュレッダーマシン (処理能力が5トン以上) |
①解体自動車の破砕を行うための施設が(産廃物処理法第15条第1項に規定する)産業廃棄物処理施設である場合にあっては、産廃物処理法第15条第1項又は第15条の2の5第1項軒邸による許可を受けている施設であること。 ②解体自動車の破砕を行うための施設が(産廃物処理法第15条第1項に規定する)産業廃棄物処理施設以外の施設(5トン未満)にあっては、産廃物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動に拠って生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設を有すること。 |
| 自動車残滓 | シュレッダーダストの保管 | ①汚水の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 ②自動車残滓の保管に伴い汚水が生じ、かつ、事業所より流出する虞がある場合は、十分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝が設けられていること。 ③雨水等により汚水の流出を防止するため、屋根、覆いその他自動車残滓に雨水がかからないようにするための施設を有すること。 ただし、十分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝が設けられている場合はこの限りではない。 ④自動車残滓が飛散又は流出することを防止するため、側壁その他の施設(コンテナ等)を有すること。 ⑤一般に自動車残滓は発火の虞があることから、適切な火災予防にも配慮する必要がある。 |
②申請者の能力にかかる基準
以下に掲げる事項を記載した「標準作業書」を常備し、従事者に周知していること
| 解体業 | ①使用済自動車及び解体自動車の保管の方法 |
| ②廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法 | |
| ③使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯)の回収の方法を含む | |
| ④油水分離装置及び溜めます等の管理の方法(これらを設置する場合に限る) | |
| ⑤使用済自動車又は解体自動車の解体によって生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く。)の処理方法 | |
| ⑥使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法 | |
| ⑦使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法 | |
| ⑧解体業の用に供する施設の保守点検の方法 | |
| ⑨火災予防上の措置 | |
| 以上規則57条第2項より | |
| 破砕業 | ①解体自動車の保管の方法 |
| ②解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、解体自動車の破砕前処理の方法 | |
| ③解体自動車の破砕を行う場合にあっては、解体じどうしゃの破砕の方法 | |
| ④排水処理施設の管理の方法(排水処理施設を設置する場合に限る) | |
| ⑤解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残滓の保管の方法 | |
| ⑥解体自動車の運搬の方法 | |
| ⑦解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残滓の運搬の方法 | |
| ⑧破砕業の用に供する施設の保守点検の方法 | |
| ⑨火災予防上の措置 | |
| 以上規則62条第2項 | |
③欠格要件(法62条、69条)
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
法人そのもの、役員及び本支店の代表者や契約締結権限のある使用人等が、禁錮以上の刑、廃棄物処理法その他の生活環境保全法令等の違反により罰金刑及び許可取り消し後から5年を経過していないこと、暴力団関係者でないことが挙げられます。
また、許可後においても欠格要件に該当した場合には許可の取り消し等の処分を受けることがあります。
更新は登録・許可ともに5年
>許可更新申請費用
解体業許可申請に必要な審査手数料については、各都道府県が設定することになっています。下記の数字は標準額です。
| 業種 | 種別 | 申請印紙料 |
| 解体業 | 新規許可申請 | 78、000円 |
| 〃 | 許可更新 | 70、000円 |
| 破砕業 | 新規許可申請 | 84、000円 |
| 〃 | 許可更新 | 77、000円 |
| 〃 | 事業範囲変更許可 | 75、000円 |
免責事項
当サイトの記載内容につきましては、万全を期していますが、保証をするものではありません。
また更新の遅れや法令改正等により文言・内容等が適合しない場合がありますのでご留意ください。法令等はお客様の個別的事情により異なる場合があり、当ホームページの記載内容だけを元に独自の法律判断に使用し、いかなる不利益や損害を受けられたとしても、当事務所は一切責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。