遺言書作成のご相談、ご依頼は石井行政書士事務所
経験と知識と知恵を駆使、あなたの期待に応えま
TEL:072-949-5214
遺言書作成のご相談、ご依頼は石井行政書士事務所
現在位置 : 石井行政書士事務所TOP >>民事法務・法人設立>>遺言書の作成
遺言書こそ、人生最大にして最後の役目
遺言書作成は遺す人の義務です。
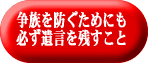 遺す人が遺言書を書き残しておくことは、遺族のためにも大事な責務であると考えます。遺言書さえあれば、もめごとの多くは解決します。
遺す人が遺言書を書き残しておくことは、遺族のためにも大事な責務であると考えます。遺言書さえあれば、もめごとの多くは解決します。
遺言書には厳格な規定が法定されています。ひとつでも欠けていれば無効となってしまいます。市販本などをよく読み。自信がなければ専門家の指導を仰ぎましょう。
作成の際、専門家に遺言執行人をお願いし、指定しておかれると後々の手続きがスムーズに運びます。
遺言の基礎知識
-
自筆遺言の場合は、ワープロや印刷はダメ! すべて自書
-
自筆遺言の最低条件は、自筆で書いた文、日付、署名、押印。
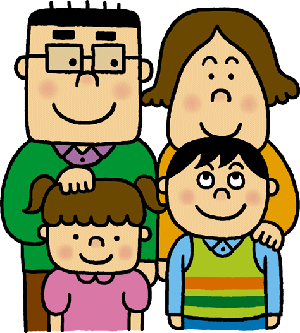
-
但し印鑑は認印でもOK
-
不動産の未登記物件は登記しておくこと
-
借金があれば隠さずに書いておく
-
ビデオは無効。必ず書面
遺言に関する法律知識
遺言の要式性 民法960条
遺言は、法律に定める方式に従わなければすることができない。
遺言能力 民法961条
満15歳に達した者は、遺言をすることができる。
遺言の方法 民法967条
遺言は、
-
自筆証言
-
公正証書
-
秘密証言
によってこれをしなければならない。ただし特別の方式(病院での医師立ち合い等)によることを許す場合は、この限りではない。
遺言の取消 民法1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を取り消すことができる。
効力発生時期 民法985条
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力が生ずる。
共同遺言禁止 民法975条
遺言は2人以上の者が同一の証言でこれをすることができない。
取消権の放棄 民法1026条
遺言者は、その遺言の取消権を放棄することができない。
公正証書遺言の作成
公正証書を作成するには本件遺言の利害に関わらない証人2人が必要です。当事務所では証人の手配も含めてお世話いたしております。
また公証役場では身体が不自由な場合やどうしても出向けない人のために、申し出れば自宅まで出向いていただけます。
公正証書を作成しますと、公証役場で原本を保管していただけます。預かり料などは一切不要です。
ところで市中の信託銀行等では公正証書を作成したら毎月預かり料を請求するところがあります。不要な費用です。どういう理由によるものなのか、よく説明を聞き、少しでも不審な点があれば問いただしましょう。
勘違いしやすい遺言のQ&A
-
公正証書で作った遺言は取り消せる?
遺言書は常に最新日付のものが有効。新たに遺言書を作成することで可能です
-
遺言執行の費用は誰が負担するの?
相続財産から支払うのが一般的です
-
受遺者が先に死亡、遺言はどうなるの?
遺贈契約はそもそも、この人だからこそ、と遺贈するもの。だから受遺者が死んだら遺贈契約は終了します
-
負担付き贈与って何?
資産だけでなくほかの負債や義務なども受け継ぎなさいという性質の贈与
-
複数枚の遺言書が出てきた。どれが有効?
最新日付のものが有効です
-
自筆証言遺言より公正証書のほうが優先?
いいえそんなことはありません。ただ公正証書は公証役場が保管保存を行うため安全なのと、裁判所の検認が不要な点です
-
遺産分割後に遺言書を出てきたらどうなるの?
遺産分割協議を原則無効となりますが、全員の合意があればすでに行われた分割は有効となります。ただし、遺産の一部が第三者に遺贈するという内容であればそれを無視するということはできません。
また相続分与を受けた財産を既に譲渡しているような場合、譲受人が相手が善意の第三者ということであれば取り返すことは難しいでしょう。このような場合、相当分を金銭で支払うよう求める以外に方策はないでしょう。
-
遺言書を隠したらどうなるの?
相続人が偶然にも遺言書を発見、自分に不利な内容だったので隠してしまったり破いてしまった場合、相続欠格ということで相続権は消失します。
また故意に隠匿、焼失、破棄、汚損、偽造変造した者も相続権を失います。
-
遺言に内妻や愛人の名前がでてきた!
遺言書は法定相続に優先します。本人の意思が反省された正当な遺言書であるかぎり、遺留分を侵害しない範囲以内なら従わざるをえません。
-
遺言信託って何?
信託法に基づく「遺言による信託」のことです。遺言によって受任した信託銀行などが遺産を管理運用し、受益者に交付するものです
-
生前の相続放棄は無効。だが死後相続権を第三者(ヤクザ)に譲渡した。どうなるの?
相続人が第三者に相続権を譲渡することは可能です。
この場合は民法905条 共同相続人の一人が分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる、とあります。
ただし、この権利行使は、一ヶ月以内に行わなければならないことになっていますので注意が必要です。
-
遺言に書かれていた預金や土地がない?
ない場合は仕方ありません。遺言そのものはもともとなかったものとみなされます。
-
代襲相続って?
本来の相続人が亡くなったため、その子が相続分を受け継ぐというものです。祖父より前に親が死んだら祖父の相続分を孫が代わりに引き継ぐということです。
-
相続時精算課税制度って何?
平成15年1月1日から施行された新しい法律です。この制度によって被相続人が生きている間に、自分の財産を相続人に相続させることができるようになりました。
家などを取得する場合、最高3500万円まで適用されます。ただし税務当局への届出が必要で、死亡時に譲り受けた資産を精算するのでこの名が付いています。
遺言による相続の廃除
普段から性格の不一致などで馬が合わないからとか、家に寄りつかないからという理由だけでは排除できません。それなりの理由が必要となります。
排除の理由
-
相続人に対する重大な侮蔑
-
被相続人に対する虐待
-
推定相続人の著しい非行
実際には遺言の記載に基づき、遺言執行者が家庭裁判所に排除の申し立てをし、家庭裁判所が審判を行い、その結果妥当と判断されれば廃除となります。
ただし、廃除された者に子がいる場合、子が相続の権利を引き継ぐことになります。
遺留分と法定相続分
いくら自分の財産だからといっても全て自分の思うままに相続させることはできません。法定で遺さなければならないとされる割合のことを遺留分といいます。
-
兄弟姉妹には遺留分はありません。諺にもあります通り「兄弟は他人のはじまり」だからでしょうかね。相続人が直系尊属のみの場合は1/3、それ以外は1/2です。
-
「全ての財産を○×NPO法人に寄付する」との遺言書が見つかったような場合、遺留分減殺請求権を行使することで認められます。
ただしこの権利には時効があって相続の開始があったことを知ったときから1年間、相続の開始の日から10年間で時効消滅します。
遺言執行人の仕事は?
遺言書の内容によってさまざまな届出等が必要となります。
-
「認知の遺言」では、就職してから10日以内に認知届出を行います。
-
「相続人の廃除の遺言」では、家庭裁判所に相続人廃除の審判申し立てを行うことになります。
-
「財産に関する遺言」では、
-
相続財産の目録を作成、それを相続人に交付する一方で管理する財産を明示する。
-
相続財産の管理や処分など遺言の執行に必要な一切の行為をする。 ・相続人が勝手に相続財産を処分したりする行為を防止する。
必ず遺言通りに分割しないとダメ?
相続人が協議によって合意を得れば遺言とは違う分割も可能。このような場合なら遺言執行者も決定した合意に従わざるを得ないでしょう。
生前の地位(保証人)はどうなるの?
まず保証人には大別すると二通りあります。
借金など債務の連帯保証人(単に保証人もある)と身元保証人です。
-
債務の連帯保証人に関してはその地位を相続します。ただしその範囲は相続分の割合で、それを超過する部分までは義務はありません。
-
債務の連帯保証人に関してはその地位を相続します。ただしその範囲は相続分の割合で、それを超過する部分までは義務はありません。
-
一方、身元保証人は一身専属的なものと解釈できますので、原則としては保証人の死によって消滅します。
営業権等の相続
個人が取得したたばこ販売業や酒類販売業の相続は可能ですが、個人が取得した建設業許可などは相続の対象とはなりません。
自動車の相続
相続できます。遺産分割協議書を添え、移転登録等の手続が必要となります。また未成年者が相続をする場合、家庭裁判所に特別代理人の選任届を提出する必要があります。